中L研
京都市立中学校教育研究会
LD等支援教育部会
*7月28日 令和7年度 中L研夏季研修会があります
夏季研修会 参加受付中(下記リンクから申し込んでください)
|
月 |
学習会・研修会・事例検討会 | 幹事会 |
| 4 | 第1回幹事会 | |
| 5 | ||
| 6 |
総会および講演会 6月11日(水)総教C |
第2回幹事会 |
| 7 | 夏季研修会 7月28日(月) | |
| 8 |
近特連研修会 コグトレ学会(東京) 幹事学習会(個別の指導計画ワークショップ・自立活動検討会) |
第3回幹事会 |
| 9 | ||
| 10 | LD学会 東京大会 | 第4回幹事会 |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 1 | 第5回幹事会 | |
| 2 |
冬季研修会 事例検討会 |
|
| 3 | 今年度まとめ | 第6回幹事会 |
*6月12日 令和6年度中L研総会が実施されました
中L研会員募集中(単年度募集、下記リンクから申し込んでください)
https://forms.office.com/r/THqmr7FvBb
8月6日(火)、下京中学校にて夏季研修会を行いました。
参加者名簿によると、会員を中心に73名の参加がありました。
第一部 個別の指導計画についての研究報告
研修会に先立ち、中L研部会長の栗陵中学校石田裕之校長よりご挨拶の後、大宅中学校通級担当の堀野大輔先生より、中L研「個別の指導計画」研究部会が作成している「個別の指導計画」について報告がありました。既存の様式を基に、より一層活用することを考えています。
報告の内容は以下の通りです。
① 個別の指導計画の様式変更のポイント
◆生徒の変容を一目で振り返れるように、3年間で1つのものを作成
◆学習面(9教科)の記入欄を1つにした
② 個別の指導計画の円滑な運用について
◆個別の指導計画についての研修会の実施
◆『こんな困りにはこんな支援リスト』の活用
◆個別の指導計画の内容を協議・共有するための学年会の設定
③ 個別の指導計画(中L研版)を活用している先生の声
◆ただ作ることだけに時間が取られる『書類』であったものが、シンプルになり、本来の趣旨である共有に向けて取り組んでいる。
◆具体的な支援方法が分からないとき、支援リストがありがたい。
個別の指導計画は学習面や生活面に支援を必要とする児童生徒の指導目標や内容、方法を具体化したものです。今後も研究を重ねていきます。
中L研版「個別の指導計画」については、大宅中の堀野まで。
第二部 講演 『ユニバーサルデザイン授業と教育の今日的課題』
京都教育大学総合教育臨床センター長の相澤雅文教授を講師として、『ユニバーサルデザイン授業と教育の今日的課題』というテーマで研修しました。
ユニバーサルデザインとは、障害の有無や年齢、性別、人種などに関わらず、多くの人々が利用しやすいように物や環境をデザインする考え方です。UDの授業では、「気になる」子への特別の配慮ではなく、「すべて」の子にとってプラスになることを目指し、授業の構成を「簡素化」「明確化」「視覚化」「共有化」することが必要。
そのための9つのポイント。
① 構造化する ;「いつ」「どこで」「何を」「どのように」すればいいのか分かりやすくすること。
例:視覚的な情報提供、教室等の空間を目的毎に分ける、合理的に分かりやすく配置する 等
② 刺激に対する配慮 ;刺激(情報)を整理し、集中して取り組めるような環境整備
例:視覚刺激の整理、聴覚刺激の整理、人的刺激の整理
③ ルールの確立 ;集団生活のルールを分かりやすく示し、共有することで生活がしやすくなる。
例:プリントや板書等のルールを統一する
④ 生活の見通しを明確にする ;「これから何をすればいいのか」「自分は今、何に向かっているのか」を視覚的に分かりやすく示す。
例:週間予定、一日の流れ、その時間の活動内容 等
⑤ 授業の見通しをもつ ;授業の流れをパターン化し、「いつまでに何をするのか」「どこまでやれば終わりなのか」など視覚的・具体的に示す。
例:授業の流れの掲示、残り時間の表示 等
⑥ 授業の組み立てを考える ;学習活動にまとまりをつくり、メリハリをつけることで集中力や意欲を保つ工夫をする
例:一斉指導とペア・グループ学習の組み合わせ、音読、小テスト、フラッシュカード、クイズ 等
⑦ 板書・提示方法の工夫 ; 板書の目的は視覚的な情報により文脈を理解し、思考を深めること
例:めあての明示、授業の全体像と流れの視覚化、学習内容の明確化、適宜確認できる、色やライン 等
⑧ 個人差への配慮 ;必要であれば、いつでも誰でも受けられることが大切
例:話すスピード、字の大きさ、分かりやすい説明、教室の環境 等
⑨ 学級モラル・人間関係の形成 ;日頃からお互いの個性を認め合う風土が培われること、「価値の多様さ」に気付けることが大切
例:助け合いや認め合いの場面の設定、集会や学級通信の活用、協働出来る機会の設定 等
| 月 | 活動内容 |
| 4月 |
第1回幹事会 組織編成、研修・事業計画、 会員募集名簿作成 |
| 6月 | 総会および勉強会(6月12日) |
| 8月 |
夏季研修会 講演(8月6日) コグトレ学会(8月18日) |
| 10月 | LD学会(10月19・20日) |
| 2月 | 冬季研修会 事例検討および講演 |
| 3月 | 活動のまとめ |
【研究テーマ】
よりそい ~連携から協働へ~
【研究目標】
LD等支援教育の充実と発展を図る視点から、多様な教育的ニーズを必要とする子どもたちを誰一人取り残さない支援の在り方について研究をすすめる
【取り組み】
①通級指導教室から通常学級につながる支援教育の推進
②「中L研版・個別の指導計画」の改善および活用
③LD等支援教育におけるICT活用
④授業UDおよびUDLの研究推進
⑤専門機関や他府県における最新情報の入手・活用
【今年度の重点】
本研究会が活動を開始して4年目を迎えた本年。通級指導教室の設置校(中)も32校となった。通常学級には、学校生活や学習に困りを抱えた生徒たちが多く在籍しており、その関連と思われる不登校の増加も喫緊の課題となっている。そのような中、通常学級における支援教育の推進および充実は何より必要となっており、本研究部会が果たす役割の重要性を痛感する。
今年度は、昨年に引き続きユニバーサルデザインな学びの実現を目指し、授業UDやUDLに関する情報収集に努め、研修会の開催および実践の促進に取り組んでいきたい。
8月2 日(木)総合教育センター にて 、 夏季研修会を行いました。 約80 名が参加しました。
「高校通級による指導 と連携」について、高校の先生から話を聞きました。
【講演】「伏見工業高等学校における通級による指導 」
講師:岡村 友加里氏(伏見工業高等学校)
「自分を知る」→「自分で目標を立てる」→「目標に向けてできることを考えて実践する」→「ふりかえる」→「改善する」という流れを大切 にしている。特に「ふりかえり」が大切。ふりかえることで自己理解が深まり、工夫したりして、生徒が変容していく姿が見られた。通級以
外の場面での生徒観察に重きを置いている。本人に 関わる 人たちへ
情報の発信や共有を行い、連携を行っている。それぞれの役割の中で生徒に寄り添い、卒業後に必要な力をつけている。
【講演2】「京都奏和高校の通級指導教室の取り組み 」
講師:小槇哲平氏(京都奏和高校)
希望者にアセスメントの上、学年、担任、通級担当で協議検討している。本人の意思(通級でやりたい・変わりたい)を確認して、対象生徒を決定している。お互いの意見をしっかりと共有して、丁寧に している。
<実践事例 について>
・なりたい自分を一緒に丁寧に考え、キャリア実践(通級)につなぐ
・自己理解のために「ふりかえり」を大切にしている。学期、行事、年間などいろいろな機会に行う。
・日頃から、授業や行事でさりげなくサポートしている
・自分達で考えて実践、経験する機会(校外学習)を設けている
・担任・学年の思いを踏まえ、連携を大切にした指導をしている
【講演】「通級指導教室との連携 」
講師:西本幸史氏(京都奏和高校)
中学校勤務から京都奏和高校準備室に異動し、現在は2年学年主任。 ヤンチャな生徒は行動や口に出すのでわかりやすいが、 「不登校」の生徒は口に出さないので、自分の思っていることや考えていることがわからない。
自己認知できるように支援を心掛けている。 本人の「強み」「弱み」 を一緒に考えて、実際に一緒に行動 しているとおっしゃっていました。
トランプ大会や球技大会(卓球・ドッチボール)などいろいろ楽しみごとを企画して、生徒たちの新たな一面が見られる。 経験を通して、学ぶ姿が見られる。
【報告】個別の指導計画(中L研版)の作成と活用について
発表:堀野大輔氏(大宅中学校)
昨年度より研究会の有志で、活用しやすい「個別の指導計画」のフォーム(様式)の作成に取り組んでいる。
個別の指導計画は「生徒理解や支援のためのツール」。開いて、更新して、つないでいくもの。しかし、活用がなかなか難しい。本人・保護者の思いが、ファイルの中で眠ってままになりがち。昨年度の検討を踏まえ、今年の総会で個別の指導計画(中 L 研版)を提案した。
<中L研版の特徴>
・3年間で1つのファイルを利用。生徒の変容を一目で振り返られる
・学習面の記入欄を1つにすることで、教科で共通の目標や教科横断的な取り組みを記載できる
総会後、「校内で共有したい」「次年度から使いたい」など反応があった。是非中L研版を利用して、ご意見をいただきたい。
中L研版に関するお問い合わせは大宅中・堀野まで。
| 部会長 | 石田裕之(栗陵) | |
| 副部会長 |
菊地順維(梅津)長谷川亜美(桃陽総合) 山口達也(向島東)野村一眞(松原)森茂昭(下京) |
|
| 幹事長 | 玉置宣子(伏見) | |
| 副幹事長 | 千代優樹(北総合中央分校) | |
| 庶務・会計 |
小山享子(衣笠)川村昌広(山科) 佐々木有利(京都御池) |
|
|
研 究
|
通級 指導 |
井本綾子(高野) 山口広美(四条) 高田夢津希(洛北)西脇優美子(北総合) 菊地浩美(桃陽総合) |
|
UD ICT |
池上賢治(藤森)今濱丈博(洛南) 平林文佳(久世)森川美希(京都京北小中) |
|
|
個別の 指導計画 |
堀野大輔(大宅)小山千栄美(大枝) 鎌谷遥(上京) |
|
| 広報 |
山口翼(洛水) 上田俊佑(北総合) 小林憂美子(西ノ京) |
|
| 教育委員会 | 大籔 晶(総合育成支援課指導主事) | |
令和5年度 京都市立中学校教育研究会LD等支援教育部会
【研究テーマ】
よりそい ~連携から協働へ~
【研究目標】
『LD等支援教育の充実と発展を図る視点から多様な教育的ニーズを必要とする子どもたちを、誰一人取り残さない指導内容や指導方法を研究する』
【取組み】
①通級指導教室から通常学級につながる支援教育
②個別の指導計画の見直しと活用
③LD等支援教育の視点からGIGAスクール構想へのアプローチ
④UD・ICT
⑤校内体制への啓発
⑥他府県での取組等
【今年度の重点】
中L研も3年目を迎え、通常学級で支援を必要とする生徒への教育の推進及び充実・発展を目指している。昨年度より書式等の見直しに取り組んだ個別の指導計画を今年度いくつかの学校で活用し、それをもとにより良いものにしている。また、ユニバーサルデザイン(UD)に基づいた授業づくり及び環境改善に取り組んでいる他市、府県の中学校の視察を行う予定である。夏季研修、冬季研修については講師を招き、LD等支援教育の充実につながる講演会を実施する。
令和5年 年間計画
| 月 | 研修会・事例検討会等 | 幹事会 |
|
4 |
第1回幹事会(栗陵中) | |
| 5 | ||
| 6 |
総会および研修会(21日) 個別の指導計画PT |
第2回幹事会 |
| 7 | 第3回幹事会 | |
| 8 |
夏季研修会(2日) テーマ;(仮)高校通級との連携 |
|
| (時期未定)学校におけるユニバーサルデザイン推進校への視察 | ||
| 9 | 第4回幹事会 | |
| 10 | LD学会(広島) | |
| 11 | 第5回幹事会 | |
| 12 | ||
| 1 | 第6回幹事会 | |
| 2 |
冬季研修会:テーマ(未定) |
冊子原稿作成 |
| 3 | 今年度のまとめ(冊子作成) | (幹事会) |
| 部会長 | 石田 裕之(栗陵中) | |
|
副部会長 |
石原廣保(桃陽総合支援)竹田久美子(向島東中) 大曽根好宏(岡崎中)長谷川亜美(呉竹総合支援) 菊地順維(梅津中) |
|
| 教育委員会 | 前川智子(総合育成支援課副主任指導主事) | |
|
役
員 |
幹事長 | 小山享子(衣笠中) |
| 副幹事長 | 千代優樹(桃陽総合支援) | |
| 庶務 |
玉置宣子(伏見中)菊地浩美(西総合支援) 小山千栄美(大枝中) |
|
| 研究部 |
小山千栄美(大枝中)菊地浩美(西総合支援) 井本綾子(高野中) 西脇優美子(北総合支援) 堀野大輔(大宅中) |
|
|
通級指導部会:山口広美(四条中)岡崎有紀(久世中) 佐々木有利(京都御池中) |
||
|
UD・ICT部会:川村昌広(山科中) 池上賢治(藤森中) |
||
| 広報 | 上田俊佑(北総合支援)山口翼(洛水中) | |
令和4(2022)年8月2日(木)総合教育センター4F永松記念ホールにて夏季研修会を対面で行い,66名の参加がありました。
【事例発表】「ICTを利用した興味・関心を高める教材」
講師:池上賢治氏(藤森中)
パソコンの解体及び組立,マイクロビットを用いたプログラミングについての事例発表でした。生徒がパソコンを分解・組立をしている様子や,プログラミングしたロボットカーを動かしている動画が提示され,生徒が試行錯誤しながら長時間集中して取り組んでいる姿が見られました。
生徒の興味や得意なことや優位なことに注目して,意欲を引き出した取組の紹介でした。
【講演】「ICTを活用した教育実践」
講師:木下 亜希子氏(京都府立清明高等学校)
清明高校のICT環境の説明,そして,学校全体で取り組まれているユニバーサルデザインと学習に困難が見られる生徒への支援,とくにICTの活用事例について紹介がありました。
清明高校で実践されているICT活用事例
① 板書の投影・配布 →板書時間、見る・書く・聞くのマルチタスク削減
② 生徒のiPadへの画面共有・画面配信
→教員の書き込みをリアルタイムで見られる、視線の往復困難や視力への支援
③ 自分のノートやカードをホワイトボードに投影する
→発表が苦手な生徒でも意見を共有することができる
④ 体育のデジタル化
→動画を撮り、客観的に自分の動きを見ることができる
⑤ 習熟度別見本動画
→音楽の器楽実技の練習を習熟に合わせて学習,教員はサポートに回る
⑥ 写真や動画(実技)のレポート、課題等のオンライン提出
→配布(提出)物がなくならない,共有が容易
⑦ Teamsでの連絡 →家で確認し直せる。聞き逃しや予定・提出漏れが減った
ICTは文具であり手段である、教具だけではなく、生徒が文具として当たり前に使えるものであるべきだ、という考えのもと、どの生徒にも適用できる合理的配慮を学校全体で実施されている様子が紹介されました。
2021年12月6日(月)上京中学校にて,北東ブロックと南西ブロック合同で事例検討会を実施しました。限られた時間で取り組めるように学校向けにアレンジした「インシデントプロセス法を取り入れた」手法を体験しました。
※「インシデント(事件,出来事)プロセス法」とは
インシデント・プロセス法とは,マサチューセッツ工科大学(MIT)のピコーズ教授夫妻により考案された事例研究法の一つです。
事例として実際に起こった出来事 (インシデント)をもとに,参加者は出来事の背景にある事実を収集しながら,問題解決の方策を考えていきます。事例研究法は,一般にケーススタディとも言われ,実際の場面で起こる問題を事例として提起・提案し,参加者が問題解決策を考えます。その過程で,参加者の分析力,判断力,問題解決能力,職務遂行能力を養うことになります。
http://www.pref.tottori.lg.jp/secure/829847/specialed5.pdf
事例検討会についてはコミュニティーページで取り上げます
(2021年8月5日 夏季研修会 於:下京中学校・後編)
【講演】「コグトレとその周辺から見る発達理解」
総合育成支援課主事 山本美紀
五感からの情報のとり入れや処理に歪みがあると,認知・実行や計画がうまく機能しない。コグトレはこの認知機能にはたらきかけている。認知機能は学校で初めて教えられることではなく,多くは就学前から身につけていくものだが,大きくなっても身につけられずにいる子がいる。
例えば,レイの図形を描かせると,プランニングや視空間のとらえ方,記憶の様子などをアセスメントできる。
支援学校勤務時,実態把握のためにやっていたこと
①家までの地図を描かせる
1本線で描く(5歳)⇒ 頭の中で道筋をたてることができる
たくさんの線で描く(7,8歳)⇒ いろいろ思い浮かべることができる
1枚におさまるように描く(9歳)⇒ 計画的に物事を考えられる
②何が一番〈コグトレより〉
三段論法;系列化操作の獲得(7歳)⇒順位決定戦ができる
6種類の順位決定戦は9歳で答えられる
③「わたしは…」を20通り書かせる
自己客観視(自分を見つめる言葉)の成立 ⇒ 9歳節を超えている
④自画像を描かせる
発達特性や家庭環境などがわかる
身体地図が分かるかどうかが分かる
⑤山あり谷ありマップを書かせる
⑥この人はどんな気持ち〈コグトレより〉
一人の気持ちよりも二人の気持ちを考えるのでは難易度があがる。
複数でやると,いろいろな価値観があることがわかる。
⑦物語づくり〈コグトレより〉
論理的,断片的に全体を考える
考えをは否定せずに聞くことが大切。
物事のとらえ方が見えてくる。
⑧心で回転〈コグトレより〉
ピアジェの三ツ山課題と似ている(9,10歳の課題)
さまざまな視点からの見え方
⑨記号さがし〈コグトレより〉
「○○しながら,○○する(同時進行)」
自分の身体や活動をコントロールするようになる(4歳半)
→ 自由自在にできるのは7歳ごろ
⑩形さがし〈コグトレより〉
形の恒常性 → マス目におさまるようになる
ひし形が描ける → 8歳6か月
斜めの概念が育っていないと「く」が書けない
発達段階における特徴と課題
○4歳半の課題
根拠をもって話す。目的をもって動く
心の理論の獲得(相手と自分の行動の違いが分かる)
自分の気持ちと相手の気持ちとを対峙する
○5,6歳の課題
「損,得」「大,小」等の両極の間の部分が分かる(系列→自己形成)
時間軸が確かなものになってくる,空間認識ができる
価値的認識(ちょっと…,どっちでもない)がつくと折り合いがつく
○7,8歳の課題
一番(系列化操作)の獲得
他者との関係の理解(説明されれば理解できる)
○9歳の課題
抽象的操作ができる。方略や作戦を考えられる
掛け算ができる(この課題を越えないと,計算はできても操れない)
筋道を立てて考える力(順位決定戦 コグトレ)
できないと後先が考えられない可能性も,上位概念が育つ
相互的な関係の理解と自己客観視(他者理解と自己理解の変化)
2021年8月5日(木)14時から下京中学校にて,夏季研修会を行いました。
研修は対面とzoomによるオンラインのハイブリットで行い,合わせて56名の参加がありました。
今回「コグトレ」に焦点を当て,前半は事例発表をしました。
【事例発表1】「通級によるコグトレの個別実施について」伏見中
・コグトレを毎週継続していくことにより,確実にできるようになるものがある。
・特に苦手としていることについては,苦手と認識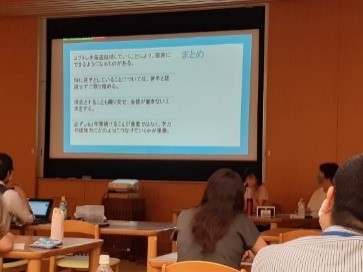
・得意とすることも織交ぜ,生徒が飽きない工夫をする。
・必ずしも三年間続けることが重要ではなく,学力や認知力にどのように
つなげていくかが重要。
【事例発表2】「朝コグトレ 学校学年実施について」衣笠中
・教室整備統一化の様子
・教科学習のウォーミングアップとしてのコグトレの利用紹介
・今年度から始めた学校全体で取り組む朝コグトレの活動内容と実施に至るまでの経緯
・学年の実態に合わせ,コグトレの内容を吟味されている
・生徒の実態に合わせてオリジナルのコグトレを作りたいという希望もある
| コグトレは認知機能の強化を目的としたトレーニングです。認知機能とは,五感を通して,情報を得て整理し,それの基に計画を立て実行し,さまざまな結果を作り出していく過程で必要な「記憶」「言語理解」「注意」「知覚」「推論・判断」といったいくつかの知的機能を指します。つまり,よりよく生きていくための機能であるといえます。(コグトレ制作者:宮口幸治 児童精神科医・医学博士) |
令和3(2021)年6月28日 中学校教育研究部会 LD等支援教育部会の設立に先立って,研修会が実施されました。
【講演】「豊かな学びを支える通級指導」
総合育成支援課専門主事 村中淳子
現在,通級指導教室 入級児童生徒数は,小学校1,009名,中学校338名。
中学校での通級指導:平成18年に試行,平成19年から本格実施。
8校からスタート→今年度29校に設置
今回のテーマ「困っている→どうしたらいいか」
実際に困っていることについて①~④を検討する。
① 誰が困っているか?生徒?保護者?教師?
② その行動が起きるのはどんな状況か? →授業?休憩時間?部活?
③ その状況の背景・要因は?
④ 集団でできる指導と個でできる指導
→結果を出すことは大事だが,プロセスの方がもっと大事。
通級指導教室ベテラン教員の「続けてきた理由や秘訣,やりがい」
「集団では見えないものが見える」→個々の生徒の困りや生徒の思い
「答えがないのが通級指導」→3年間の成長をイメージ。生徒と一緒に楽しむ
「通級のことがわかってくれる人が増えた」→校内での支援や指導体制の確立
「生徒にとって通いたいと思う教室を目指して」→通級のプロとして
「話を真剣に聞く」→趣味を共感して,初めて信頼感が生まれる
最後に「豊かな学びを支えるために」
①「3年間の成長をイメージしながら」
②「通いたい魅力的な通級を目指して」
③「支援や指導の仲間も増やしていこう」
【第1回(設立)総会】
設立趣旨の説明や年間計画などが承認され,研究会が発足しました。
その後,部会長,副部会長をはじめ,役員が紹介されました。
【幹事長よりごあいさつ】小山享子(衣笠中)
第1回総会を実施し,研究会がいよいよスタートしました。
創立にあたり,尽力いただいた皆様,また当日総会に参加いただた皆様ありがとうございました。
LD等支援教育の充実と発展を図る視点から,多様な教育的ニーズを必要とする子どもたちへの指導内容や方法を研究していきたいと考えています。
今後ともご協力よろしくお願いします。
☆中L研だより(9月号)発行しました
R6中L研だより9月号.pdf
☆中L研だより(6月号)発行しました
R6中L研だより6月号.pdf
中L研だより(3月号)発行しました(3月11日)
中L研だより(1月号)発行しました(1月28日)
中L研だより1月号・日本発達障害学会第58回研究大会報告.pdf
中L研だより(11月号)発行しました(11月10日)
中L研だより(9月号)発行しました(9月4日)
中L 研だより(7月号)発行しました
京都市立中学校教育研究会LD等支援教育部会コミュニティページへのログインはこちら



